民泊の運営を始める上で、知っておきたいのが「180日ルール」です。
このルールは、民泊新法(住宅宿泊事業法)によって定められており、年間の営業日数が180日以内に制限されています。
法規制を順守しつつ、最大限の収益を上げるためには、このルールの詳細や対応策をしっかり理解することが不可欠です。
この記事では、180日ルールの概要や背景、制限を超えるための方法、そして黒字化を目指すための成功ポイントまで徹底解説します。
民泊の180日ルールとは?

民泊の180日ルールとは、2018年6月に施行された住宅宿泊事業法(通称:民泊新法)により定められた、年間の営業日数制限のことです。
この法律により、民泊として運営可能な日数は年間180日以内に制限されています。
この規制は、適切な運営基準を設けることでヤミ民泊を排除し、地域の住環境を保護する目的で導入されました。
民泊新法(住宅宿泊事業法)で定められたルール
住宅宿泊事業法では、民泊として運営するために一定の基準を満たす住宅が対象となります。
主な基準は次の通りです。
- 設備要件(台所や浴室、トイレ、洗面所など生活に必要な設備の整備)
- 居住要件(実際に生活が可能な状態であること)
さらに、営業可能な日数は1年間で最大180日までと制限されています。ただし、自治体によってはさらに短縮される場合があります。
民泊として運営するには、事前に都道府県知事に届け出を行う必要があります。
この届け出には、
- 物件の所在地
- 所有者情報
- 管理方法
などを詳しく記載します。
法律を守って運営することで、地域住民や利用者からの信頼を得られ、信頼性の高いサービス提供が可能になります。
民泊の180日ルールができた理由と背景
民泊の180日ルールが導入された背景には、
- ホテル業界への悪影響を軽減させるため
- ヤミ民泊の問題解消をするため
- 騒音やゴミ問題を解決するため
への対応が挙げられます。
ホテル業界への悪影響を軽減させるため
民泊の急成長により、低コスト運営が可能な民泊がホテル業界に大きな競争圧力を与えていました。
特に地方や中小規模のホテルは、価格競争で顧客を失うリスクが高まっていました。
180日ルールによって民泊の営業日数を制限し、観光業全体のバランスを保つとともに、ホテル業界への悪影響を軽減する目的があります。
ヤミ民泊の問題解消をするため
許可を得ずに営業する「ヤミ民泊」は、税金未納や管理不足などの問題を抱え、地域住民や行政に負担をかけていました。
このルールは、届出制を義務化することでヤミ民泊を排除し、安全で管理が行き届いた宿泊環境を整備するために導入されました。
違法営業を減らすことで、民泊業界全体の信頼性向上を目指しています。
騒音やゴミ問題を解決するため
民泊利用者が引き起こす騒音やゴミの放置は、地域住民の生活に悪影響を与えていました。
特に都市部や住宅街では、民泊増加に伴いトラブルが頻発していました。
180日ルールは、民泊運営者に地域社会との調和を促し、利用者のモラル向上や運営管理の強化を求める制限です。
これにより、地域住民と民泊の共存を目指しています。
民泊の180日ルールで押さえるべき基礎知識

民泊の営業可能日数は年間180日以内とされていますが、その数え方に注意が必要です。
営業日数のカウント方法
営業日数は「正午」を基準に計算されます。
例えば、以下の場合を考えてみましょう。
- チェックイン:4月1日正午
- チェックアウト:4月2日15時
この場合、営業日は2日とカウントされます。
スケジュールを組む際は、この計算方法を正確に理解することが大切です。
物件ごとの適用ルール
180日ルールは、物件ごとに適用されます。
複数の物件を運営している場合、それぞれの物件が180日以内に制限されます。
同じ管理者でも物件ごとに日数を管理する必要があります。
地域ごとの追加規制
自治体によっては、用途地域や家主の居住状況に応じて営業日数がさらに短縮される場合があります。
特に住宅街や都市部では厳しい制限が設けられていることが多いため、営業予定地域の規制を事前に調査することが重要です。
ルールを正しく守ることで、効率的な運営と地域社会からの信頼を得ることができます。
自治体ごとの180日ルールの違いと対策

自治体が定める4つのルールパターン
民泊の営業可能日数は全国一律ではなく、自治体ごとに異なるルールが設定されています。
これらの規制は主に以下の4つのパターンに分類されます。
1. 日数制限がない自治体
一部の自治体では、追加の営業日数規制がなく、年間180日の範囲内で自由に運営できます。
- 特徴:運営が比較的しやすく、日数管理の負担が少ない
- 対象地域:規制が緩やかな地域
2. 用途地域による制限がある自治体
住居専用地域では、平日の営業が制限される場合があります。
- 特徴:平日は営業できず、土日祝日のみの営業になるケースが多い
- 影響:年間の稼働日数が約120日程度に縮小される可能性あり
3. 用途地域と不在型で制限がある自治体
用途地域の制限に加え、不在型民泊が平日に禁止される場合があります。
- 特徴:不在型では平日営業が不可だが、家主居住型なら制限が緩和されることも
- 対応策:運営形態を家主居住型に変更するなどの調整が必要
4. 区内全域で平日営業が不可な自治体
地域全体で平日の営業が禁止される、最も厳しい規制です。
- 特徴:営業は週末に限定される
- 影響:稼働日数が大幅に減少し、収益性が制限される
- 対象地域:住宅街や観光地など、住民の生活を優先する地域
自分のエリアでの制限を調べる方法
民泊を運営する際には、地域ごとの規制を事前に確認することが重要です。
特に東京23区では、各区が独自の「上乗せ条例」を定めており、営業可能日数や条件が異なります。
これらの情報は各区の公式ウェブサイトや窓口で確認できます。
また、地元の民泊業者や不動産会社に相談することで、実践的なアドバイスを得られる場合もあります。
事前に十分な調査を行い、各自治体の規制に従うことで、スムーズな民泊運営が可能となります。
民泊の180日ルールを超える方法と抜け道

180日ルールを回避する4つの方法
民泊の180日ルールは運営の大きな制約ですが、特定の方法を利用することで、年間を通じて運営することも可能です。
以下の4つの方法を検討してみましょう。
| 簡易宿所にする
(旅館業法の許可を取得) | 旅館業法の「簡易宿所営業」の許可を取得すれば、180日の制限を受けずに365日運営可能 ただし、消防法や建築基準法の要件を満たす必要があり、申請プロセスはやや複雑許可取得に成功すれば、合法的に通年営業できる利点がある |
|---|---|
| 特区民泊にする
(認可地域での運営) | 国家戦略特区として認められた地域で運営する場合、特区民泊として365日営業が可能 この方法は、設備要件が比較的緩やかで、許可の取得が容易対象地域には、東京都大田区や大阪市などがある |
| マンスリーマンションとして運用 | 民泊の180日間以外の期間を利用し、1か月以上の中長期契約を行うマンスリーマンションとして運用する方法 この形態は民泊の枠組みを超えており、安定収益を見込める点が魅力 |
| レンタルスペースとして併用 | 宿泊以外の用途で、時間貸しのレンタルスペースとして活用する方法もある リモートワーク、撮影スタジオ、女子会など多目的に利用されることで、稼働率を高めることが可能ただし、レンタルスペースとして運用する場合は、事前に利用可能な時間帯や設備を明確にしておく必要がある |
民泊の180日ルールを活用した初年度360日運営の方法
民泊の180日ルールは毎年4月1日から適用されますが、この仕組みを活用すると、初年度に最大360日運営することが可能です。
この方法を利用するには、以下の手順とポイントを押さえておきましょう。
仕組みの概要
- 営業開始を10月1日に設定
初年度の残り期間(10月1日~翌年3月31日)の180日間を営業。
次年度(4月1日~9月30日)の180日間も引き続き運営可能です。 - 合計360日運営が可能
初年度の180日と新年度の180日を合わせて連続運営が実現します。
具体例
- 営業開始日:10月1日
- 初年度の営業期間:10月1日~翌年3月31日(180日)
- 次年度の営業期間:4月1日~9月30日(180日)
必要な準備
- 申請のタイミング
営業開始前の9月末までに届出を完了する必要があります。 - スムーズなスタートを計画
開始直後に予約が埋まるとは限らないため、事前の宣伝や運営準備を早めに進めることが重要です。
注意点
この方法はルールを厳密に守りながら行う必要があります。違反が発覚すると信頼性を損ない、営業停止のリスクもあるため注意してください。また、自治体ごとの規制も事前に確認し、営業スケジュールを立てる際に反映させましょう。
民泊の180日ルールを守らなかった場合の罰則とリスク

民泊新法では、年間180日を超えて営業を行うことが禁止されています。
このルールを守らずに営業を続けた場合、法律違反となり、罰則やさまざまなリスクが発生します。
罰則について
180日ルールを違反した場合、民泊新法自体に罰則規定はありませんが、旅館業法に基づき処罰される可能性があります。
具体的には、6か月以下の懲役または3万円以下の罰金が科されることがあります。これは、無許可で旅館業を営んだとみなされるためです。
その他のリスク
営業日数超過が発覚すると、以下のような行政措置が取られる場合があります。
- 物件のリスティング(掲載)の停止
- 事業者登録の取り消し
これらの措置により、運営そのものが難しくなる可能性があります。
ルールを守ることで、信頼を失わず、安定した運営を続けることができます。
定期報告の虚偽申請に関する罰則
民泊新法では、事業者に営業状況を定期的に報告する義務があります。
この報告内容に虚偽があった場合、最大30万円以下の罰金が科される可能性があります。また、以下のリスクも伴います。
- 行政の信頼を失い、運営停止命令や事業者資格の取り消し措置を受ける可能性
- 事業の継続に大きな影響が出るリスク
正確な記録を保持し、報告義務を誠実に果たすことが重要です。
具体的には、宿泊者名簿の管理や営業日数の記録を徹底する仕組みを整えることが求められます。
Airbnbでのルール違反と影響
定期報告のAirbnbを利用して民泊運営を行う場合、登録物件が年間180日を超えて予約されると、リスティングが自動的に非表示になります。
これはAirbnbが法律を遵守し、利用者が意図せずルールを破らないようにするための措置です。
複数の予約プラットフォームを併用している場合、各プラットフォームの予約日数を合算して管理する必要があります。
特に繁忙期には予約の重複や営業日数の超過に注意が必要です。虚偽申請に関する罰則
よくある質問(Q&A)でさらに理解を深める

家主不在型民泊はどの程度難しいのか?
家主不在型民泊は、家主が物件に常駐せず、物件全体を宿泊施設として提供する運営形態です。
このタイプの民泊は収益性が高い一方で、管理や法規制の面で難しさがあります。
まず、物件が住居専用地域に位置している場合、営業日数や用途地域に応じた厳しい規制が適用されることがあります。
また、家主不在型では騒音やゴミ問題が発生しやすく、近隣住民とのトラブル防止が重要です。
そのため、民泊管理業者を利用するなど、適切な管理体制を整える必要があります。
さらに、不在型の場合、清掃や鍵の受け渡しなどを委託するコストも発生します。
これらの要素を考慮し、利益を確保するための綿密な計画が求められます。
180日を超える場合にどれを選ぶべきか?特区民泊vs旅館業法
年間180日以上の営業を希望する場合、「特区民泊」と「旅館業法」のどちらを選ぶべきか、迷うこともあるでしょう。
それぞれの特徴を理解し、物件や地域に適した選択をすることが重要です。
|
特区民泊
|
旅館業法
|
| 国家戦略特別区域に指定された地域で、特定の条件を満たすことで365日営業が可能
施設基準や申請手続きは比較的簡単で、最低宿泊日数も2泊3日に緩和されている 特区民泊が認められている地域では、手軽に運営を始められる | 旅館業法の簡易宿所として許可を取得すれば、どの地域でも365日営業可能
ただし、消防法や建築基準法に基づいた厳しい施設要件が課されるため、許可取得までのコストや時間がかかる その分、信用度が高まり、高価格帯の客層をターゲットにする運営が可能 |
地域の規制や運営コストを比較し、自分のビジネスモデルに合った選択をしましょう。
まとめ:民泊の180日ルールを理解し、成功する運営を目指そう
民泊の180日ルールは、法律を順守しながら適切に運営するための重要な規制です。
このルールを理解し、物件や地域の特性に応じた運営方法を選ぶことが、成功への第一歩です。
また、規制に縛られることなく収益を最大化するためには、特区民泊や旅館業法を活用する選択肢も検討すべきです。
さらに、SNSやOTAを駆使した集客戦略、魅力的な部屋作り、そしてコスト管理を徹底することで、短期間でも黒字化を目指すことが可能です。
本記事で紹介した基礎知識や成功のポイントを参考に、法律を守りつつ安定した収益を確保できる民泊運営を目指しましょう。
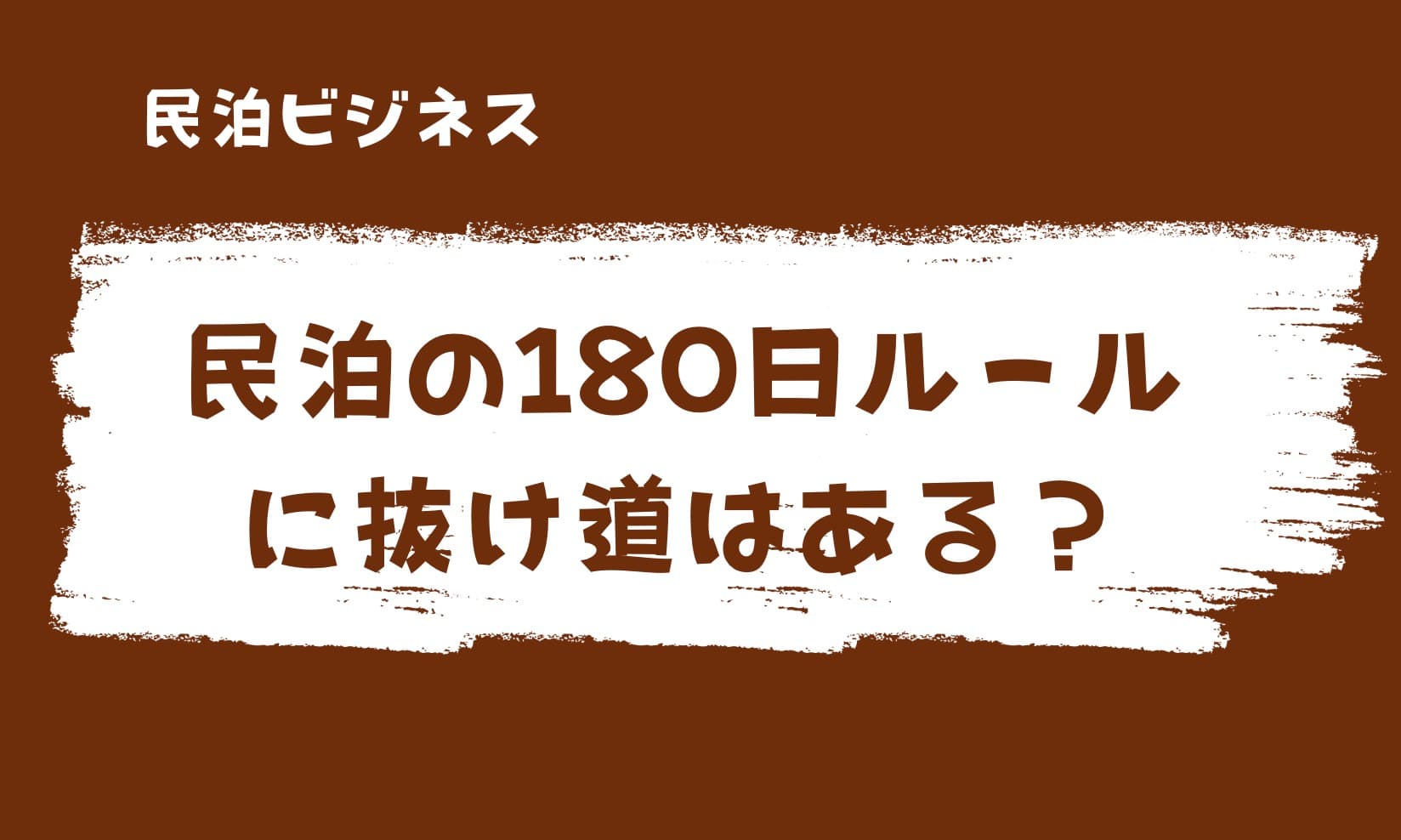
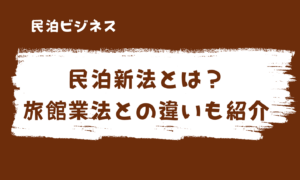
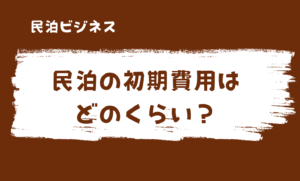
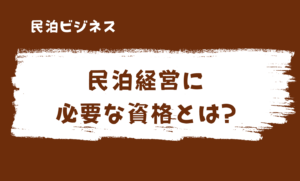
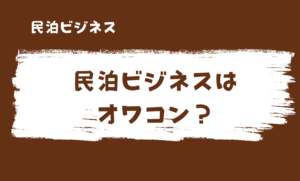
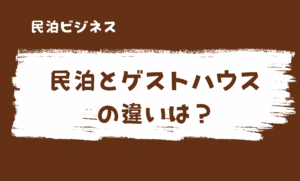
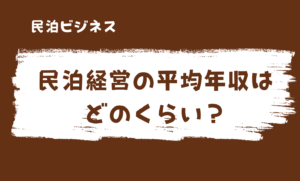


コメント